2015年11月13日
☆中・高年の方々に一筆啓上! ④
☆中・高年の方々に一筆啓上! ④ 「氣」について
以前に、このブログで養生の3つ目として、「氣の養生」について述べました。そして、江戸時代の
益軒先生が、「氣」は人の生の根源であると『養生訓』で語っておられ、当時のベストセラーになった
ことは、庶民一人ひとりが養生の達人だったかもしれません。貧しかろうが病気だろうが、日々の
生活を楽しむ要領を知っていたような氣がするのです。
その「氣」が今どきも良く使われています。氣の基本は生命エネルギー~「氣」を使った言葉が
いっぱいあります。少し、列記してみましょう。(私たちは、「氣」と「氣功」という時に、この「氣」を
使っています。「気」の中の「メ」では閉じこめるからダメ。「氣」のなかの「米」は四方八方に広がる
というのでここでは、気を「氣」という漢字を意識的に使ってみます)
「氣分」「氣力」「氣配」「氣品」「氣質」「氣前」「氣楽」「氣概」「氣絶」「氣鋭」「氣迫」「氣風」「氣候」
「氣温」「氣節」「病氣」「活氣」「勇氣」「本氣」「強氣」「弱氣」「語氣」「眠氣」「人氣」「元氣」「平氣」
「才氣」「色氣」「浮氣」「陽氣」「殺氣」「呑氣」「天氣」「空氣」「景氣」「電氣」「大氣圏」「空氣感」
「雰囲氣」とあって、「氣後れ」「氣疲れ」「氣取る」「氣位い」「氣高さ」「氣構え」「氣休め」「氣合い」
「氣苦労」「氣負う」「氣落ち」「氣立て」「氣の毒」「氣づく」「氣紛れ」「氣移り」「やる氣」「勝ち氣」
「心意氣」「生意氣」「氣を使う」「氣にする」「氣になる」 まだまだあります。
「氣が合う」「氣まずい」「氣が重い」「氣が回る」「氣掛かり」「氣が散る」「氣を配る」「氣晴らし」
「氣に病む」「意氣込む」「味氣ない」「根氣強い」「産氣づく」「負けん氣」「氣がゆるむ」「氣がついた」
「氣が引ける」「氣にかける」「氣色が悪い」「氣嫌がいい」「氣にしない」「お氣に入り」「氣骨がある」
「氣が滅入る」「氣が晴れる」「熱氣がある」「若氣の至り」「精氣を養う」「勝手氣まま」「氣っ風がいい」
「氣持ちいい」「氣脈を通じる」「氣のない返事」「意氣に感じる」「氣乗りしない」「氣むずかしい」
「氣勢を上げる」「氣が大きくなる」「呆氣にとられる」「からだに氣をつけて」「氣を許せる仲間・場所」
「スキップしたい氣分」など、挙げるときりがありません。(入力していて、氣疲れしました。もう、この
へんで止めます。) では、これら言葉の「氣」とは一体、何でしょう・・・?。
目に見えるものではないが確かにあるのではないでしょうか? これほどの多様な言葉があると
いうことは、昔から「氣」というものが身近に存在していた証(あかし)なのでしょう。 「氣の養生」の
「氣」とはこんなにも氣遣い・氣配りするくらいのものなのです。
私たちが稽古を積んでいる「氣功太極拳」は、深くて長い呼吸によって「氣」を養い、ゆっくりとした
理にかなった動きです。筋肉を弛緩(しかん)させ、円く(まる)く螺旋(らせん)の運動、波動の動き
なのです。これにより、血の流れを良くし、経絡の交差点にあるツボを刺激しますから、「氣」を
養うのに最適な体術なのです。この「氣」を練ることを「氣功」といっています。
ここまで説明して、少しは「氣功と太極拳」の良さをご理解していただくことが出来たでしょうか?
アタマで理解できてもダメです。畳の上で泳いでいるようなもので水泳の練習とはならないでしょう?
やはり、実際に先生についてカラダを動かさねばなりません。独習はなかなか難しいと思いますヨ。
72歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
以前に、このブログで養生の3つ目として、「氣の養生」について述べました。そして、江戸時代の
益軒先生が、「氣」は人の生の根源であると『養生訓』で語っておられ、当時のベストセラーになった
ことは、庶民一人ひとりが養生の達人だったかもしれません。貧しかろうが病気だろうが、日々の
生活を楽しむ要領を知っていたような氣がするのです。
その「氣」が今どきも良く使われています。氣の基本は生命エネルギー~「氣」を使った言葉が
いっぱいあります。少し、列記してみましょう。(私たちは、「氣」と「氣功」という時に、この「氣」を
使っています。「気」の中の「メ」では閉じこめるからダメ。「氣」のなかの「米」は四方八方に広がる
というのでここでは、気を「氣」という漢字を意識的に使ってみます)
「氣分」「氣力」「氣配」「氣品」「氣質」「氣前」「氣楽」「氣概」「氣絶」「氣鋭」「氣迫」「氣風」「氣候」
「氣温」「氣節」「病氣」「活氣」「勇氣」「本氣」「強氣」「弱氣」「語氣」「眠氣」「人氣」「元氣」「平氣」
「才氣」「色氣」「浮氣」「陽氣」「殺氣」「呑氣」「天氣」「空氣」「景氣」「電氣」「大氣圏」「空氣感」
「雰囲氣」とあって、「氣後れ」「氣疲れ」「氣取る」「氣位い」「氣高さ」「氣構え」「氣休め」「氣合い」
「氣苦労」「氣負う」「氣落ち」「氣立て」「氣の毒」「氣づく」「氣紛れ」「氣移り」「やる氣」「勝ち氣」
「心意氣」「生意氣」「氣を使う」「氣にする」「氣になる」 まだまだあります。
「氣が合う」「氣まずい」「氣が重い」「氣が回る」「氣掛かり」「氣が散る」「氣を配る」「氣晴らし」
「氣に病む」「意氣込む」「味氣ない」「根氣強い」「産氣づく」「負けん氣」「氣がゆるむ」「氣がついた」
「氣が引ける」「氣にかける」「氣色が悪い」「氣嫌がいい」「氣にしない」「お氣に入り」「氣骨がある」
「氣が滅入る」「氣が晴れる」「熱氣がある」「若氣の至り」「精氣を養う」「勝手氣まま」「氣っ風がいい」
「氣持ちいい」「氣脈を通じる」「氣のない返事」「意氣に感じる」「氣乗りしない」「氣むずかしい」
「氣勢を上げる」「氣が大きくなる」「呆氣にとられる」「からだに氣をつけて」「氣を許せる仲間・場所」
「スキップしたい氣分」など、挙げるときりがありません。(入力していて、氣疲れしました。もう、この
へんで止めます。) では、これら言葉の「氣」とは一体、何でしょう・・・?。
目に見えるものではないが確かにあるのではないでしょうか? これほどの多様な言葉があると
いうことは、昔から「氣」というものが身近に存在していた証(あかし)なのでしょう。 「氣の養生」の
「氣」とはこんなにも氣遣い・氣配りするくらいのものなのです。
私たちが稽古を積んでいる「氣功太極拳」は、深くて長い呼吸によって「氣」を養い、ゆっくりとした
理にかなった動きです。筋肉を弛緩(しかん)させ、円く(まる)く螺旋(らせん)の運動、波動の動き
なのです。これにより、血の流れを良くし、経絡の交差点にあるツボを刺激しますから、「氣」を
養うのに最適な体術なのです。この「氣」を練ることを「氣功」といっています。
ここまで説明して、少しは「氣功と太極拳」の良さをご理解していただくことが出来たでしょうか?
アタマで理解できてもダメです。畳の上で泳いでいるようなもので水泳の練習とはならないでしょう?
やはり、実際に先生についてカラダを動かさねばなりません。独習はなかなか難しいと思いますヨ。
72歳、高齢者・障がい者後見人のブログです。
Posted by 黑田よしひろ at 16:50
│ブログ



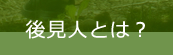
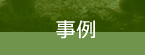
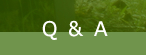
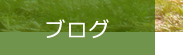





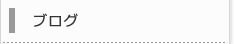



 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン















